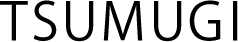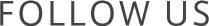ドミニカ共和国食べもん日記
旅先から帰る。「どうだった?」と感想を聞いてくる家族や友達に、「良かったでー!○○が美味かったわ!」と、二言目にはいつも食べもんの話をしているような気がする。
食べることが大好きで、美味いもんに巡り会っただけで「あぁーええとこやなぁ」と思える。土地の印象は食べもんで決まるのだ。
そんな私は今、JICA海外協力隊としてカリブ海の島国、ドミニカ共和国へ派遣されている。
任地は国東部のアト・マジョール。特産品がオレンジやレモンであることから、「Capital del Cítrico(柑橘類の都)」とも呼ばれている。柑橘類の他にも、街の周囲に広大なサトウキビ畑が広がっていたり、放牧地で牛たちがのんびりと草を食んでいたり、日本では見かけないユカ芋、カカオ、コーヒーなどの農園が点在していたりと、農業が盛んな州だ。
食事は毎食ドミニカ料理。主にホームステイ先で家庭料理をいただいている。
朝、ホストマザーが淹れてくれたコーヒーを飲むと、寝ぼけ眼が覚めて「今日もドミニカ社会の一員として働くかー」という気分になる。食堂で地元のおじさんと肩を並べアビチュエラを食べていると、自分の存在が土地に溶け込んでいくような感覚になる。一日の終わりに、ステイ先のお孫さんたちがおどけている隣でプラタノを頬張っていると、本当の家族に近づけたような気がする。
一食一食、ドミニカ色に染まっていく――
本エッセイでは、食いしん坊な私が、ドミニカ共和国の食卓や食堂はもちろん、台所や畑など「食の現場」で出会ったひと、もの、ことから心動かされたことを綴る。
食を通して、読者の皆様のドミニカ共和国のイメージが膨らんでいくような連載にしたい。
不定期連載、編集担当は野田です。

JICA海外協力隊(青年海外協力隊)としてドミニカ共和国東部のアト・マジョールに暮らす。任期は2019年4月から2021年4月まで。志賀直哉が「うまいものなし」と評した奈良県出身の27歳。うどんが好き。
1.甘いコーヒー
ドミニカ共和国生活7ヶ月目に入った日の夜のこと。いつものようにホストマザーが「タカ、コーヒー飲む?」と聞いてきた。
我が家では、朝は食前、夜は食後にコーヒーを飲むことが多い。
私が飲みたいと答えると、彼女は立ち上がりキッチンに向かう。この光景も、繰り返される日常の一コマとなってきた。
しばらくすると、コーヒーの湧いた音が聞こえてきた。
ホストマザーはエスプレッソ用の小さなカップを持ってキッチンから姿を現したが、そこで急に、手の甲を額に当てるようにして大きな声で笑い始めた。
突然の出来事ではあるが、5ヶ月も一緒に暮らせば、その理由は想像がついた。
どうやら私のコーヒーにも、砂糖を入れてしまったようだ――

ドミニカ共和国では、コーヒーにたっぷりの砂糖を入れて飲むことが多い。
どれくらいたっぷりかというと、ホットコーヒーを飲みほしたカップの底に、溶け切らなかった砂糖がどろどろと溜まるぐらい。あるいは、保温ポットに入れた甘いコーヒーの香りに誘われて、虫が集まってくるぐらい。
先日、参加したフィエスタ(お祭り)でコーヒーをいただいた際は、口を付けた瞬間、あまりの甘さに頭がクラっとした。
甘いコーヒーもたまに飲むくらいなら悪くないのだが、毎日のこととなると、やはり辛い。そこで、家では無糖のコーヒーを淹れてもらうようにしていたのだ。
私がこの激甘コーヒーを初めて飲んだのは、首都サント・ドミンゴでの研修を終え、いよいよアト・マジョールに着任するという日だった。
地方都市へ派遣される隊員は、それぞれの配属先から迎えが来て、任地まで送ってもらうことになっていた。私の場合は、上司と同僚の男性が来てくれた。
首都から任地までは車で約2時間。男3人の車内は、初対面の外国人を乗せたちょっとした緊張感があり、私は気まずさを覚えていた。
海沿いの道を走行中、上司がドライブインにハンドルを切った。休憩を取るらしい。
ビーチ客と思しきドミニカ人に混ざり、テラス席に腰を掛けると、彼は私の同僚となる男性にいくらかお金を渡し、コーヒーを買いに行かせた。
プラスチック製の使い捨てカップを3つ持って戻ってきた同僚から、コーヒーを受け取り、一口飲むと、想像以上の甘さに面食らってしまった。
「甘いですね」
上司に、簡単なスペイン語で伝えてみる。
「そうだろ!コーヒーは好きか」
「無糖のコーヒーが好きです」
「なんてっこった!そりゃ苦いだろ!」
上司と同僚は顔を見合わせ、笑い始めた。
その後しばらく上司と同僚の会話を聞いていると、駐車場からドミニカ人女性客らがこちらに向かって手を振っているのに気付いた。
珍しいアジア人をからかっているのかもしれないが、嫌な気はしなかったので、手を振り返してみる。すると、キャッキャと騒いで車に乗り込んでいった。
上司が聞いてくる。
「ドミニカの女は好きか」
「ええ!好きですよ!」
さきほどこの国のコーヒーの飲み方を否定したばかりなので、少しおどけてリップサービスをすると、彼は笑いながら「アト・マジョールで彼女を見つけないとな」と言った。
大きなお世話だよと思いながら、少しだけ彼らと打ち解けたような気がした。
――その日から約5ヶ月、ホストマザーが淹れてくれたコーヒーに口を付ける。
あれ……?
優しい甘さだった。加糖ならぬ“過糖”コーヒーに慣れ始めていたのか、程よい甘みに驚いてしまう。これなら美味しくいただける。
「美味い!美味いよ!」
私が伝えると、ホストマザーは、ほんとに!と言わんばかりに目を見開いた。
「明日から砂糖入りにする?」
「あ、いや、やっぱり苦いやつで」
私が間髪入れずに答えると、彼女はあっははははーと明るく笑った。
あと1年半、私はこの国の人たちを何度笑顔にできるだろう――
そんなことを思いながら、私はもう一口温かいコーヒーを口に含んだ。