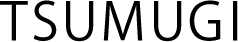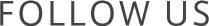ドミニカ共和国食べもん日記
旅先から帰る。「どうだった?」と感想を聞いてくる家族や友達に、「良かったでー!○○が美味かったわ!」と、二言目にはいつも食べもんの話をしているような気がする。
食べることが大好きで、美味いもんに巡り会っただけで「あぁーええとこやなぁ」と思える。土地の印象は食べもんで決まるのだ。
そんな私は今、JICA海外協力隊としてカリブ海の島国、ドミニカ共和国へ派遣されている。
任地は国東部のアト・マジョール。特産品がオレンジやレモンであることから、「Capital del Cítrico(柑橘類の都)」とも呼ばれている。柑橘類の他にも、街の周囲に広大なサトウキビ畑が広がっていたり、放牧地で牛たちがのんびりと草を食んでいたり、日本では見かけないユカ芋、カカオ、コーヒーなどの農園が点在していたりと、農業が盛んな州だ。
食事は毎食ドミニカ料理。主にホームステイ先で家庭料理をいただいている。
朝、ホストマザーが淹れてくれたコーヒーを飲むと、寝ぼけ眼が覚めて「今日もドミニカ社会の一員として働くかー」という気分になる。食堂で地元のおじさんと肩を並べアビチュエラを食べていると、自分の存在が土地に溶け込んでいくような感覚になる。一日の終わりに、ステイ先のお孫さんたちがおどけている隣でプラタノを頬張っていると、本当の家族に近づけたような気がする。
一食一食、ドミニカ色に染まっていく――
本エッセイでは、食いしん坊な私が、ドミニカ共和国の食卓や食堂はもちろん、台所や畑など「食の現場」で出会ったひと、もの、ことから心動かされたことを綴る。
食を通して、読者の皆様のドミニカ共和国のイメージが膨らんでいくような連載にしたい。
不定期連載、編集担当は野田です。

JICA海外協力隊(青年海外協力隊)としてドミニカ共和国東部のアト・マジョールに暮らす。任期は2019年4月から2021年4月まで。志賀直哉が「うまいものなし」と評した奈良県出身の27歳。うどんが好き。
2.白いドゥルセ・デ・ナランハ
ホームステイがはじまって6ヶ月。私とホストファミリーの関係は、普通か、あるいは良好だと思っている。
必要があれば話すし時々雑談もするが、無理に話すことは無い。彼らとの間に沈黙が流れても、それは決して気まずいものではない。
こんな風に書くと、なんだか本当の家族のようだが、一方で、自分はゲストなのだと感じることもある。食事の際、みんながフォークだけで食べているのに私にはナイフが付いてきたり、私だけ少しきれいなコップでジュースが出てきたり、彼らは鍋から“直食い”することも多いが、私の食事は必ず皿に盛りつけられていたり……
こうしたゲスト待遇も寂しくはない。彼らなりのおもてなしなのだろうと思うし、何より、言葉もできず見た目も違う外国人の私を、半年ほどの月日で真の家族として受け入れるなんて、無茶な話である。
家族であり、ゲストでもある。
ホストファミリーとの生活は、私にとっては居心地が良く、彼らのことを、数少ない、心許せるドミニカ人だと思うようになっていた。
そんな家族と過ごす土曜の夜。リビングから私を呼んだのはホストファミリーの娘さんだった。
「はーい」と投げやりな返事をすると、コーヒーが入ったとのこと。
重たい腰を上げてリビングに行くと、ホストマザーが遅めの夕食を取っていた。
食べているのはインスタントラーメンだが、我が家ではこれをsopa(ソパ)と呼んでいる。つまり、スープである。
食べ方もスープさながらで、箸はもちろんフォークも使わず、スプーンで食す。それもそのはず、麺は調理段階でバリバリと砕かれ、スープの具になるのだ。
初めて食べた時、インスタントラーメンみたいな味やなぁと思ったが、その正体を知って内心苦笑したのを覚えている。
ホストマザーの隣に腰かけ、娘さんからコーヒーを受け取る。一口飲むと、この日はきっちり苦かった。
ホストマザーが話しかけてくる。
「このソパ、タカがこないだ日本製って教えてくれたやつよ。私これ好きなの」
「あぁ……」
なんだか会話が面倒に思えた。こんな気持ちになるのは、ホストファミリーに対しては初めてかもしれない。
「タカはこのソパ好き?」
「うん、好きだよ」
早く会話を終わらせて、自室に帰ってしまいたかったが、何となく席を立つタイミングを逸してしまった。
普段の私なら、「よっしゃ!スペイン語の練習や!」という意識も働いて会話を続けようとするのだが、この日はただでさえいい加減なスペイン語で、テキトーに相槌を打ち続けた……
思えば、この日は朝から調子の出ない一日だった。
週に一度の洗濯も面倒。それでも洗わないことには翌週着る服がないので、自分に鞭打ち庭に置いてある洗濯機を回す。なのに、途中でそぼ降る雨に見舞われた。
洗いの済んだ衣類はタライでジャブジャブすすぐのだが、止み間を見ながらやったためいつもの倍ほどの時間がかかり、しかも洗濯物はパリッと乾かず、ため息でもつきたい気分に。
負の連鎖は続き、ここ数日真面目に取り組んでいたスペイン語の勉強も放り出し、日課のランニングもイマイチ身体が重かった。
ホストマザーとの会話を億劫に感じたのは、そんな日の夜だった。
一つ一つの会話が長続きせず話題があちこちへ転がるなか、私のボランティアとしての活動の話になった。どうやら彼女は、私の同僚の実家で作られているDulce de Naranja(ドゥルセ・デ・ナランハ)に興味があるらしい。
dulceは「甘い菓子」、naranjaは「オレンジ」、つまり「オレンジの甘い菓子」である。アト・マジョールの特産品であるサトウキビの絞り汁を煮詰め固めたもので、これまた特産のオレンジが混ぜ込まれている。食べてみると黒糖特有の甘みが口の中に広がり、柑橘の爽やかな香りが鼻から抜けていく。
甘党の私でも甘すぎると感じるが、ドミニカ人はこのドゥルセが大好きで、色んな種類のものが売られている。

同僚の実家で作られているドゥルセ・デ・ナランハ
コーヒーを飲み干し、そろそろ部屋に帰るかと思った頃、ホストファザーがビニール袋を持ってのそのそと現れた。
肉付きの良い、それでいてゴツゴツした手で、彼は袋の中から何かをちぎり取り、私に「食べてみろ」と渡してきた。
乳白色の塊を指で摘まんでみると、ベタつきを覚える。塊の中にはオレンジの皮のようなものが見えた。
「ドゥルセ・デ・ナランハ?」
こくりと頷くホストファザー。
サトウキビの絞り汁を煮詰めるだけでなく、精製のひと手間を加えたドゥルセのようだ。
どうせならコーヒーがなくなる前に食べたかったなと思いながら一口かじってみると、見た目の通り黒糖の風味はなく、マーマレードをただ固めたような味がした。これを洗練と呼ぶのかもしれないが、私にはいささか面白みに欠ける味のように思える。あるいは、この味を肯定的に受け取れないのも、気分の問題だったのかもしれない。
傍らに座る私をよそに、両親は何かを話し始める。まだまだドミニカ人同士の会話は聞き取れない。
彼らの会話を無感動に眺めながらただ甘いだけの塊をかじっていると、さっきまでの自分の態度がふいに思い出された。
まるで反抗期やないか……
私の機嫌の悪さを、彼らがどこまで感じ取っていたのかは分からない。
ただ、夫婦であり4人の子を持つ親でもある彼らの会話を眺めていると、ふと、自分はこの家の息子なのだと思えてきた。
先ほどまでの思春期真っ盛りみたいなそっけない素振りがちょっと恥ずかしかく、お世話になっているドミニカ共和国の両親に、たまには親孝行の一つでもしないといけないなと思えた。